銚子ポートタワーとウォッセ21を最後に銚子・犬吠埼を離れます。 今日はお嫁さんが東京湾フェリーに乗りたい! とのことでしたので、銚子から東京湾フェリーの港「金谷港」に向かいます。 でもせっかくなので、途中にある「久留里城」を観光していくことにしました。
銚子からは、少し一般道を走り、その後、銚子連絡道路⇒圏央道に出て南下していきます。 途中、東京アクアラインや都心の首都高速の渋滞表示が出ていましたが、アクアライン含め都心は相当渋滞していましたね。
あんな渋滞にはまるのであれば、急ぐ旅でもないし、フェリーで帰ったほうが楽ですね^^
ただ、ビックリしたのは、銚子連絡道路という有料道路に乗ってから、1時間以上パーキングがないですっ! 先ほどの山一いけすさんで結構お茶を飲んでしまったので、管理人のタンクはフルタンク! 早くトイレに行きたかったのですが、ナビにも全然PAの文字が出てきませんでした。 出発してから約2時間でようやく高滝湖PAの文字がっ! なんとか車を汚さずにすみました^^ この後は木更津のICで降りて、一般道で久留里城まで向かいます。 久留里城の資料館の開館時刻が16:30まででしたので、結構ギリギリの到着になりました。 (でも、あまりに坂がきつすぎてお嫁さんのテンションが下がってしまったので、資料館はスルーして天守だけ見て帰りました^^;) |
ようやく待ちに待ったパーキングエリアに到着しました。 こちらのパーキングエリアは千葉県市原市にある首都圏中央連絡自動車道のパーキングエリア。 上下一体型の構造で、圏央道としては千葉県内唯一の休憩施設なんだそうです。
名称は、近くにある高滝ダムのダム湖「高滝湖」から取られていて当初は「市原高滝湖SA」としてサービスエリアとしての供用を予定していました。
|
 |
唯一のパーキングエリアの割には何にもないなぁ。。。 売店もないしトイレくらいしかありません。 でも、よくよく見ると、PAの建物の裏側に三角錐をした巨大な丘が・・・ 更に注意してみると、登っている人がいるぞ!
なんか上にあるのかな!? ということで登ってみました。 そうしましたら、頂上から高滝ダムのダム湖「高滝湖」がよ〜く見えましたよ。
車を停めている場所からは全然湖は見れませんで、登らないとこの湖をみることができません。 今日は天気もよく眺めは最高! PAにこのような施設があるのは初めて見ましたよ。
|
 近くに来てみると、結構巨大な丘ですよ! |
 PAの駐車場の先に湖が綺麗に見ました |
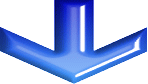
 |
久留里城は別名「雨城」・「霧降城」・「浦田城」と呼ばれています。 「城の完成後、3日に一度、21回雨が降った」とか「この山にはよく霧がかかり、遠くから見ると雨が降っているように見え、城の姿が隠し覆われ敵の攻撃を受けにくかった」ともいわれているそうです。 「西」氏と管理人みたいです^^;
久留里城の起源については「平安時代中期の猛将平将門の三男、東少輔頼胤が初めてこの地に砦を構えた」と伝えられていますが、確証はなく伝説と考えられています。 室町時代には上総武田氏の武田信長によって古久留里城が建てられ、以降は信長の子孫である真里谷氏が支配しました。
戦国時代、真里谷氏は衰え、代わって里見氏の拠る所となり、里見氏によって再構築され(新久留里城)、佐貫城と共に対北条氏の最前線を担いました。 その後、江戸時代には久留里藩の藩庁として再整備され、酒井氏の加増地となり、その後近世城郭として明治維新まで維持されました。
久留里城の復元は旧上総町のころに明治百年事業として計画され、地元はもとより多くの市民から待ち望まれていました。 そして昭和53年に天守閣が完成し、約100年ぶりに久留里の丘陵に城が再建され、翌年には久留里城址資料館も完成しました。
天守閣は、城山公園の本丸跡の隣りに築城され、鉄筋コンクリートの2層3階建て、延べ面積は約190平方メートル、高さは15mあります。 石垣は、安山岩を2mの高さに積み四方にまわし、外壁は昔の城と同じように、白の漆喰壁と南京下見板風につくられています。 久留里城は、房総半島の中・近世城郭の代表格として、また周囲に残る数々の遺構は貴重な資料として、往時の面影を今に伝えています。 |
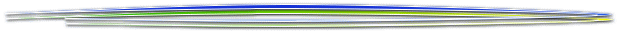
久留里城は山城なので、一般道からわき道にそれて、大分山を上ったところにあります。 駐車場はもちろん無料でした。 駐車場周辺や天守周辺にもお土産やさんがなく寂しい観光地ですね〜。 資料館の閉館時刻が間近ということもあり、車も我々を含めて3〜4台しか停まっていませんでした。
駐車場から「久留里城天守」と書かれた看板に向かって歩き出します。 すると駐車場のすぐそばに杖を格納している箱がありまして、10本位の杖が入っておりました。 ちょっとちょっと〜、この杖があるってことは・・・ この先は大分登るってことですよねぇ。。。
先のほうを見ると・・・ビンゴ! 先の見えない急坂が待っておりました>_<
|
 杖があるぅぅぅぅ |
 ものすごい坂があるぅぅぅぅ |
これは大分急な坂ですね〜。 ものの1分で、2人共無言になりました・・・ 話すことがないってことではなく、もう息が上がってしゃべれない感じね^^; しかも午前中から色々歩き回った後だから・・・ でも道が舗装されていて歩きやすくなっていたのは救いでしたね〜。
途中の看板を見ると、本丸の標高は145m。 二の丸が128m。 そして現在の標高は55m。。。 まだまだ結構ありますね^^;
坂道の途中には、当時の面影を残す遺構、曲輪がいくつかありましたよ。 例えば写真左にあるのは「久留里曲輪」。 曲輪というのは郭とも書きますが、城の防御や、攻撃するために造成した平場の区画を言います。 こちらの久留里曲輪はそんなに広くはないですが、城の周囲にはこのような曲輪がいくつも設けられています。 また右の写真は堀切の跡です。 堀切というのは山頂に向かう際に一番進みやすい尾根の筋を切り取って行軍しにくくした堀のことです。 こちらの堀切には平時には橋が掛けられていたそうです。 |
 こちらは久留里曲輪です |
 堀切跡です |
こちらが久留里城の資料館です。 城の二の丸に資料館が建てられています。 入館は無料ではありましたが、前述の通りもう二人ともダウンのため資料館はスルー。 少し心残りではありましたが、今回はさすがに管理人も急坂を歩き続け、死亡推定時刻3分後の状態でしたので諦めがつきました。
後で調べてみると、こちらの資料館は君津市の歴史・民俗などの資料や久留里城に関する資料の収集、保管、展示がされているそうです。 |
 |
 |
山麓の近世居館部は一部の土塁を除き開発により消滅しましたが、車道で一部が削られたものの山上の遺構は比較的よく残り、天守台等の近世遺構に加え、堀切や削り残し土塁等の中世里見氏時代の遺構も見られます。
また、山上は湧水が豊富で、男井戸・女井戸、お玉が池を始めとする、複数の水源が現在でも水を湛えています。
|
 お玉が池がひっそりと水をたたえています |
 男井戸・女井戸と2つの井戸があります |
急な坂を耐え忍び、ようやく天守までたどり着きましたよ。 がんばって登ってきた甲斐あって、綺麗な天守を見ることができました。
もちろん現存天守ではないので、中身はマンションのようですが、やっぱり天守の外観は良いものですね。 天守の横には実際に天守があった基礎がそのままありましたよ。 天守を見ると「大きいあ〜」と感動することが多いですが、意外に基礎の部分って狭く感じるのよね。 不思議^^;
一番そう思ったのは安土城。 すごく壮大な城のイメージの割に、基礎は狭いんですよね。
|
 |
 |
 |
 |
 |
天守は2層3階建てということですが、中には他のお城の写真(城にいくとたいてい他の城の写真がかあってありますよね^^;)が展示してあるくらいで、何の展示物もありません。 そのまま階段を登って最上階へ。
最上階では後から来たお若いヤンキー風のカップルがイチャイチャしておりました。 天守最上階からの景色はなかなか良いものです。 天守後ろのほうは森しか見えませんが、正面側は抜けがよくてルーラルな景色が情緒的です。
いつも天守まで登って景色を見ると、それまでの疲れが飛んでいく感じがします。
|
 こちらは1階です お約束の城の写真 |
 階段はこんな感じです |
 最上階に到着しました |
 外の廊下は結構狭いです |
 最上階から下をのぞくとこんな感じ |
 山深いところに建っているのが分かります |