首都高速湾岸線から東関東自動車道に入り冨里ICで降りました。 東関東自動車道は以前「岡」氏と鹿島港に釣りに行っていたころによく通ったんですよね〜。 久々に通りましたが、懐かしいな〜。
成田山新勝寺に行くのに冨里ICで降りましたが、この後、午後には犬吠埼に行くため、東関東自動車道の潮来まで行き、更にそこから銚子に向かいました。 正に釣りに行ったときのルートそのままなので、ホント懐かしく感じました。
さて冨里ICで降りた後は、一般道で成田山新勝寺に向かいます。 途中JR成田駅前を通りぬけ、冨里ICから約20〜30分位でしょうか。 最初は住宅地の中を走り抜けていくような感じだったのですが、途中から急にお寺感を感じさせる通りに変わります。 うわ〜すごく雰囲気ありますね〜。 成田山新勝寺の周囲には有料の駐車場がいくつもありますし、到着時刻が9:20頃と早めだったこともあり、一番近い町営の駐車場に停めることができました。 一日停め放題で800円。 でも観光を終えて帰ってくると、あれだけ広かった駐車場も満車に近い状態でしたよ。 平日でこれだと、休日なんて車停められないね。 さすが成田山ですね! |
 |
 |
成田山新勝寺は、千葉県成田市成田にある真言宗智山派の仏教寺院であり、同派の大本山の一つである。 山号は成田山。 山号を付して「成田山新勝寺」、あるいは山号のみで「成田山」と呼ばれることが多い。
本尊は不動明王で、当寺は不動明王信仰の一大中心地である。 そのため、成田不動、お不動さまなどといった通称でも広く親しまれてきた。 開山は平安時代中期の天慶3年(940年)と伝えられる。寺紋は葉牡丹。
参詣者数において関東地方屈指の寺である。 初詣の参拝客数は、社寺としては明治神宮に次ぐ全国第2位(千葉県内第1位)、寺院に限れば全国第1位の参拝客数である。 今も昔も加持祈祷のために訪れる人が多いことでも知られる。 by wikipedia
|
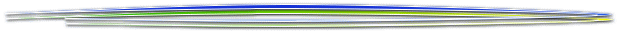
町営駐車場に車を停めて外に出てみると、もう結構気温が上がっていましたよ。 天気予報では気温が下がるといった予報も出ていたので、管理人もフリースやパーカーなども持参したのですが、一日目は上着どころか、半袖Tシャツで十分な気温。
特に成田山新勝寺の境内はとても広く、時にアップダウンもあるので、あっという間に汗ビショビショになってしまいました^^;
|
 成田山新勝寺の入口にそびえる「総門」です |
町営駐車場から成田山新勝寺の総門までは徒歩1分で到着です。 総門から道路を挟んで反対側には割と広い広場がありまして、この広場から総門をいい感じで激写することができました。 他の観光客の方も、ここから記念撮影をされていましたね。 しかしここの総門はとても立派ですね〜。
遠くから見ても厳かさが伝わってくるようですが、近寄って細部を見ると、遠くから見た迫力とは反対に、造形や装飾がとても繊細なんですよね〜。 木の組み方とか、絶妙な曲線を描いた建築物などかなり目を引きますね。
こちらの総門は開基1070年の記念事業により、2008(平成19)年に建立されたんだそうです。 意外に新しいですね^^; 高さ15mの総欅造りで、蟇股という欄間にあたる部分には十二支の木彫刻が施されています。 また、楼上には八体の生まれ歳守り本尊が奉安されています。 成田山の表玄関として、多くのご参詣者をお迎えしています。 |
 総門には山号の「成田山」の文字があります |
 総門の横にある「成田山新勝寺」と掘られた石柱 |
総門をくぐりぬけると、約50m位の参道が続きます。 参道の両脇には色々な石塔が立っていました。 その先には登り階段があり「仁王門」が現れます。 先ほどの総門よりは一回り小さいように見えますが、こちらも非常に趣深い建物ですね〜。
中心には大きな提灯がぶら下げられていますよ。 なんとなく浅草の浅草寺の門を思い出すようです。 門の両脇にはいかめしい像が2体。 こちらは密迹金剛、那羅延金剛というんだそうです。 この裏側には広目天と多聞天が守っていました。
大体こういうのって金網が張ってあるから、ピントが合いにくいのですよねぇ。。。
|
 |
 |
こちら仁王門は、1831(天保2)年再建の国指定重要文化財です。 門の左右に密迹金剛、那羅延金剛の二尊が奉安され、昔から成田山の門を守ってきました。 中央の「魚がし」の文字が大きく目立つ大提灯は、魚河岸講の奉納によるものなんだそうです。
この仁王門は国指定の重要文化財とありましたが、成田山新勝寺には重要文化財が非常に多くありましたよ。 この後もご紹介していきましょう。
|
 |
 |
 多分こちらが那羅延金剛 |
 こちらが多聞天かな!? |
成田山新勝寺の境内はとても広くて、総門から大本堂以外にも色々な建物があります。 この先にある「大本堂」の左側には「釈迦堂」「出世稲荷」が、また右側には「三重塔」「聖徳太子堂」などもあります。 また大本堂の更に奥には「平和大塔」という大きな塔もありますし、更に平和大塔の横にはかなり広い公園が広がっています。
先ほどの仁王門から大本堂に行く間にも、いくつかの見どころがありました。 仁王門から大本堂に行くための階段まで30mくらいしかないのですが、その間にはお地蔵さんを祀った社もありますし、亀の形をした石が鎮座する池(本物の亀もいましたよ)もありますし、なんだかよくわからない社もあります。 ちょっと数が多すぎて、一つ一つ見るのは大変ですよ^^; |
 何体かのお地蔵様 |
 中央の石が亀の形していますよ |
 階段があったので行くのやめました^^; |
 亀のいる池を渡る橋が架かってました |
仁王門を通り過ぎ、階段を上がると目の前に大本堂が見えてきます。 大本堂前はとても広い広場になっていますね。 初詣のときにはここにズラリと参拝客が並ぶんでしょうね〜。 先ほど通ってきいた総門や仁王門に比べると、随分新しい建物だな〜という印象を持ちました。
説明を見てみると、大本堂の建立は1968年(昭和四十三年)とのことなので、こちらも管理人とほぼ同い年になりますね。 思ったほど新しくはなかったですが、もしかしたら建物の造形が意外にシンプルで、かつ壁が綺麗な白塗り、屋根が綺麗な緑色というのもあって、あまり古く感じなかったのかもしれません。
大本堂は成田山新勝寺で最も重要な御護摩祈祷を行う中心道場です。 堂内の御本尊不動明王は、向かって右に矜羯羅童子、左に制咤迦童子を従えています。 また、四大明王や平成大曼荼羅などが奉安されているそうです。 こういう寺社や建物は撮影できても、ご本尊などの撮影は禁止されているので、残念ながら不動明王様の写真はありません。 ご本尊はしっかりと自分の目に焼き付けていきたいと思います。 |
 |
大本堂の右側には見事な三重塔がありました。 神社や寺社に行くと、三重塔や五重塔があるところが多いですよね。 個人的には形状がとても良いなとか、心柱という工法などの技術のすごさなどに感心しながら見ているのですが、そもそも〇重塔って何!?
wikipedia で調べてみると「仏教の祖である釈迦の舎利(遺骨)をおさめる仏塔の形式の一種。」と書いてありました。 そうなんだ〜お釈迦様のご遺骨が納められているのですね〜。 仏塔のルーツは古代インドで、紀元前3世紀頃から造られ始めたストゥーパに起源をもつんだそうですよ。
成田山新勝寺の三重塔は1712年(正徳二年)年に建立された重要文化財です。 総高は25mで、塔内には大日如来を中心に五智如来が奉安され、周囲には「十六羅漢」の彫刻がめぐらされています。 雲水紋の彫刻がほどこされた各層の垂木は一枚板で作られた珍しいもので、一枚垂木と呼ばれています。 近くで見ますと、装飾や色も非常に見事です。 遠くからの眺めも良いですが、近くで木の組み合わさりや、装飾を見学するのも良いものですよ。 |
 |
 |
三重塔の更に右側には「一切経堂」という建物があります。 建物自体はとてもシンプルですね。 「経堂」というのは、経典を納めておく建物のことで、経蔵とも言います。
こちらの一切経堂は1722年(享保七年)年に成田山中興第一世照範上人によって建立され、これまで多くの修復を繰り返してきました。 堂内の輪蔵には、仏教の集大成である一切経(約2,000冊)が納められています。 入口の額は、松平定信公の筆によるものなんだそうです。 輪蔵周囲の桟唐戸には四天王と十二神将の彫刻が施されており、八体の鬼神が支えています。 |
 |
一切経堂の更に奥には「聖徳太子堂」という建物です。 遠くから見たときに、奈良の法隆寺にある夢殿に似ているな〜と思っていたのですが、やっぱり聖徳太子にかかわる建物だったみたいです。
こちらの建立は1992年(平成四年)年で、2007年(平成十九年)年に修復されたそうですので、まだ新しいですね。 日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられたんだそうです。
こちらは珍しく、撮影禁止のマークがなかったので、中の聖徳太子をパチリしておきました。
|
 |
 |
これまでは、大本堂に向かって右側のエリアを見学してきましたが、今度は左側に行ってみます。 左側にも色々あるようですよ。 こちらは「出世稲荷」です。
御本尊は、江戸時代に成田山をあつく信仰した佐倉藩主・稲葉正通が寄進されました。 商売繁昌、開運成就、火伏せのご利益があると伝えられており、古くから出世稲荷と呼ばれて親しまれているそうです。
面白いのが、出世稲荷の正面の鳥居横にはキツネの好きなお揚げを販売しており、ここでお揚げを買ってから、出世稲荷にお供えするようになっていました。 まだ朝早いということもあって、4〜5個のお揚げがお供えしてありましたが、休日なんてお揚げが山盛りになりそうですね^^
|
 |
 |
 |
 |
全然関係ないですが、こちらの出世稲荷のすぐ外は、境内への出入り口になっていました。 管理人達は正面玄関にあたる「総門」から入りましたが、ここからも入れるみたいですね。 こちらの参道の両脇には写真のようにお土産屋さんがズラリと建ち並んでしましたよ。
まだ時間が早いからなのか、新型コロナの影響で店を閉めているのか分かりませんが、ほとんどシャッター街で、空いているお店は2〜3軒しかありませんでした。 もしかしたら、ここらへんって木曜日が定休日のお店が多いみたいなので、そのせいかもしれません。
|
 |
こちらは釈迦堂です。 位置としては大本堂の左側のエリアです。 1858年(安政五年)年に建立された重要文化財です。 かつての本堂であり、大本堂の建立にあたって1964年(昭和三十九年)年に現在の場所に移されました。
仏教を開いた釈迦如来や、普賢、文殊、弥勒、千手観音の四菩薩が奉安されています。 周囲には、五百羅漢や二十四孝の彫刻がほどこされ、江戸時代後期の特色をよく残している総欅づくりの御堂です。 厄除お祓いの祈祷所です。
建物は五間堂で、中央の柱間が広くとられています。 屋根は入母屋造の瓦棒銅板葺で、正面には千鳥破風や軒唐破風付きの向拝を設けています。
|
 |
いや〜結構、境内を歩き回りましたが、まだまだ2/3位でしょうか。 相当広いし見どころが多いです。 これは朝一発目にもってきて正解でしたよ。 これが午後だともう足が終わって全部回りきる前に途中で帰ってましたよ。
最近足がすぐに終わってしまうので、長い時間歩くのは無理なんですよね〜。 あとここはちょくちょく階段とか坂道が多い>_<
さ〜これまで総門から境内に入り、正面の大本堂、右側の三重塔や聖徳太子堂、そして左側の釈迦堂、出世稲荷を見学してきましたので、今度は大本堂の更に奥の平和大塔、成田山公園を見学に行こうと思います。 |
 |
参道を進んでいきますと、またまた階段がありまして、そこを登ると正面に「額堂」が姿を現します。 「額堂」は1861年(文久元年)に建立された重要文化財で、1986年(昭和六十一年)に修復されました。
ご信徒から奉納された額や絵馬などをかける建物で、江戸時代に奉納された貴重な絵馬や、様々なモチーフの彫刻は、目を見張るものがあります。 また、七代目市川團十郎丈が寄進された石像があります。
これは歌舞伎の方なんでしょうかね。。。 あまり興味がない分野なので、一応石像の写真は撮ったのですが、HPには載せませんでしたm(_ _)m しかしここまで重要文化財は何個あったでしょうかね〜。
見る建物、見る建物がどれも重要文化財に指定されているので、少しだけありがたみが減少してきてしまいました^^;
|
 |
 |
額堂のすぎ先にには「光明堂」がありました。 なんとこちらも重要文化財! 更にありがたみ減! 正面には「愛染明王」の看板が立ってました。 境内には色々な建物があって、そこに色々な神様が祀られていますね。 聞いたことがあるような神様が多かったです。
ちなみに成田山新勝寺の本尊「不動明王」は、大日如来の化身とも言われていますし、先ほどの「愛染明王」も明王の一人なので、如来の化身となっています。 「愛染明王」は名前とは裏腹に、怒った憤怒相をしています。
「光明堂」は1701年(元禄十四年)に建立されました。 釈迦堂の前の本堂であり、江戸時代中期の貴重な建物です。 大日如来、愛染明王、不動明王が奉安されています。 後方には奥之院の洞窟があり、毎年、祇園会に開扉されます。 奥の院の洞窟は、奥行きは約11mあり、正面に不動明王の本地仏である大日如来が安置されています。 扉の左右にある板碑はとても貴重なものなんだそうですよ。 |
 光明院の建物です |
 光明院の裏にある奥之院の入り口です |
光明院を過ぎてしばらく進むと、平和大塔の頭の部分が見えてきましたよ。 とても大きな塔ですよね。 こちらの塔は1984年(昭和五十九年)に建立されました。 真言密教の教えを象徴する塔となっています。
総高は58mで、1階は大塔入口、成田山の歴史展、写経道場各種受付があります。 2階の明王殿には、大塔の御本尊不動明王、四大明王、昭和大曼荼羅、真言祖師行状図が奉安され、3・4階の経・法蔵殿には、ご信徒による掛仏、5階の金剛殿には五智如来が奉安されています。
我々は階段を上がったところでお参りしますが、中を見ますと、かなり大きな不動明王様がものすごい怖い顔をしておりました。 不動明王の周りには4体の明王がこれまた怖い顔で立っておりました。
平和大塔の横には「醫王殿」がありました。 こちらはまだ大分新しい建物ですね。 こちらの建立は2017年(平成二十九年)と言いますから、まだできたばかりですね。 開基1080年祭記念事業として建立されたもので、木造総檜、一重宝形造の御堂には薬師瑠璃光如来、日光菩薩、月光菩薩、十二神将が奉安されています。 健康長寿と病気平癒の祈祷所です。 でもさすがに平和大塔の存在感が大きすぎて、全然目立ってないですね^^; |
 |
 遠くに平和大塔のてっぺんが! |
 左が「醫王殿」右に「平和大塔」があります |
 平和大塔を左側から激写 |
 平和大塔を正面から激写 |
平和大塔のすぐわきに「成田山公園」という看板がありました。 境内のマップを見た絵で確認すると大本堂の右奥に広大な公園があるようですね。 せっかく来たのですから、どんな公園なのか散歩しながら総門に戻るようにしようと思います。 資料を見てみますと、こちらの公園は東京ドーム約3.5個分もあるんだそうですよ。
公園内には美術館などもありました。 さすがにここまで大分歩いてきて足が終了間際になっているので、公園内全部を歩いたり、美術館を見学したりすることはしませんでしたが、園内は綺麗に整備されていて、非常〜〜〜に綺麗な公園でしたよ。 滝や池、石に群生しているコケなど非常に心が洗われるようなすばらしい公園でした。
しかもここは犬などの家畜を連れての散策が禁止されているので、管理人も安心です^^
|
 入口を入るとまずは下り階段です |
 入ってすぐは背の低い木々が並びます |
 池に流れ込む川にかかる橋、こういう橋いいよね |
 コケの写真!これは今日一の良い写真です |
 せせらぎの音が心地よいです |
 雄飛の滝・・・が逆光でネロになってしまった |
 雄飛の滝のそばには御滝不動尊があります |
 池の周囲の木々が少しだけ紅葉してました |
いや〜成田山公園はホントに良かった。 久々に滝のマイナスイオンを感じましたし、木々からの木漏れ日に反射したマイナスイオンが見えましたもん。 これはメチャメチャ気持ち良かったですね。 でもそれとは反対に足はすでに終わり始めています>_<
そろそろ次に行きますか! ということで総門に向かって歩き始めましたが、あれあれあれ!? これまだ見てないよ!? もう敷地が広すぎて、全部余すことなく見学できているかすごく不安ですね。
こちらは、仁王門のそばにあった「石摺不動尊」です。 何か石に不動明王が彫刻されているんですよ。 こちらに彫刻された不動明王は1827年(文政十年)に中興第八世照胤上人が建設し、その後天保十三年に第十世照阿上人が再開眼されたものです。 以来、石摺不動尊として信仰されているんだそうです。 仏像もいいけど、こういう不動明王様もなかなか良い感じがしますね。 |
 入口を入るとまずは下り階段です |
 入ってすぐは背の低い木々が並びます |
いや〜しかし、見どころがホントに盛りだくさんでしたね。 9:15に総門をくぐったのですが、帰ってきたのが10:50ですよ。 約1時間半強歩き回っていましたね。 でも初成田山新勝寺はすばらしところでした。 ではではお次はここらで昼飯を食しに行ってきますか!
|