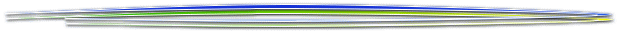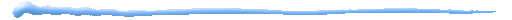
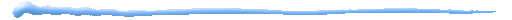
本日は、埼玉県はさいたま市大宮にある「鉄道博物館」に行ってまいりました。
実は管理人は「隠れ鉄」でありまして、通勤電車は最高に嫌いですが、
旅行などに行くと、その土地の電車の写真を撮ってしまいます。
管理人が小学生のころは、鉄道ブームで、横浜駅、東京駅、上野駅など さまざまな駅に出向き、電車の写真を撮ったものです。 実はこの鉄道博物館は 管理人は2回目のご来店なのです。 1回目のご来店は現在の鉄道博物館の前身の 「交通博物館」。 確か小学生低学年だったような気がします。 当時の所在地は 秋葉原だったような気がします。 交通博物館の閉館は2006年。 今回訪れた 鉄道博物館は2007年10月に開館したそうです。 今回なぜ鉄道博物館に行ったのか!? と申しますと、現在期間限定(2010年10月〜2011年1月)で 御料車のイベントを実施しているからです。 御料車とは日本の天皇や後続の方々が乗車する車両のことです。 今回の鉄道博物館には、初代1号、初代2号、7号、9号、10号、12号御料車が展示されています。 今回は特別イベントということで、御料車に設置されていた玉座や装飾品などが特別展示され、また 御料車の特別見学も可能でした。 それでは鉄道博物館、御料車などご紹介します。 |
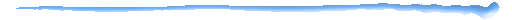
〜 鉄 道 博 物 館 入 場 ! 〜
鉄道博物館は埼玉新都市交通伊奈線の鉄道博物館(大成)駅にあります。 今回は自動車で行きましたが、
自動車で横浜から行くと、東名高速⇒首都高渋谷線⇒首都高中央環状線(この新しい道路、非常に便利!)⇒
首都高池袋線⇒首都高埼玉大宮線で与野ICから一般道で約15分位で到着します。
駐車場は旧引き込み線の線路の跡地がそのまま駐車場になっており、非常に広いです。
3連休の初日だったにも関わらず、すんなり駐車場に入れました。
駐車場から徒歩3分で入場口に到着します。 料金は大人1,000円、子供500円です。 入場口の前にチケット販売機があり、そこでチケットを購入します。 チケットはSUICAに似せたIC チップのカードです。 これを自動改札機に似せた入口にかざして入場します。 凝ってますね。 |
|
|
|
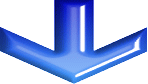
〜 御 料 車 展 〜
鉄道博物館を入り、エスカレータで2階へ。 上がってすぐのところに御料車の特別企画展が開かれています。
残念ながら内部の撮影は禁止のため、写真はありませんが、玉座を初めて数々の品。。。もうそれは美術品と言って
いいと思いますが、多数展示されています。 また珍しいのは御料車の当時の設計図なども展示されていました。
御料車の装飾品はその時代時代の最高のものを結集して作成されるそうです。 織物、置物、金具、扇風機に
いたるまで、神々しさを感じずにはいられません。
|
|
|
|
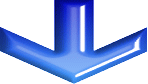
〜 鉄 道 歴 史 年 表 コ ー ナ ー 〜
御料車展を見終わり、そのまま2階のフロアーを歩くと、鉄道歴史年表コーナーがあります。
実際に年表が横にずらーーーっと記述されているのですが、なんでも長さは75mもあるそうですよ。
ここには昔懐かしい電車のミニチュアや、ヘッドマークなどが展示されています。 管理人が子供の頃によく乗った
ブルートレインや、見たこともないような名称のヘッドマークなど非常に興味深いです。
|
|
|
|
|
|
|
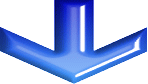
〜 ヒ ス ト リ ー ゾ ー ン 〜
鉄道歴史年表を見終わったら、お待ちかねのヒストリーゾーンです。 このゾーンには昔に活躍した各種車両を
展示しています。 またこのゾーンは車両を見るだけでなく、電車の運転台を実際に操作し、実際に連動した車輪が
駆動するといったシミュレーションや、昔ながらの木造の客車のシートに座ったり、子供にもうれしい工夫がたくさんあります。
全部ではないですが、管理人のお気に入りの車両をご紹介したいと思います。
|
 |
ここの展示車輌の中で最も気に入っているのが、こちらのC57蒸気機関車です。 管理人の中ではC62と並び最も
好きな蒸気機関車です。 昔、旅行で山口県に行ったときに「山口号」という車輌が走っており、これを牽引していたのがC57だったのです。
その際はチケットの抽選に外れてしまったため乗車することはできませんでしたが、子供ながらに線路そばで
一生懸命写真を撮ったのを覚えています。
C57形蒸気機関車は、旧国鉄の旅客用テンダー式蒸気機関車です。 「貴婦人」の愛称で有名ですが、蒸気機関車・鉄道ファンは 「シゴナナ」と呼びます。 製造は1937年〜1953年で製造車両数は215両だそうです。 軸配置は4−6−2。 全国の旅客列車の牽引を中心に使用されました。 |
 |
こちらの車輌も思い出深いです。 小学生の頃に横浜駅まで写真を撮りに行き、初めて自分で撮ったのがこの車輌でした。
この頃(1970年代)は貨物列車も寝台列車もEF65に並びEF58が牽引していました。
EF58形電気機関車は、旧国鉄の旅客用直流電気機関車です。 1946年から1948年にかけて初期型車が製造されましたが、 31両が完成したところで諸事情により一旦製造中止となっているそうです。 1952年以降、全くの別形式となるほどの大改良を 経て量産を再開。以後、初期型車も車体載せ替えを含む仕様統一の改造を受け、1958年まで増備されました。 のべ製造両数は172両です。 |
 |
このボンネント型に憧れて鉄道辞典などを毎夜見ていたような記憶があります。 ですが、この特急形車輌は管理人は走っているところを
見たことがないと思います。 ボンネント型は1980年代最初の頃まで運用されていたため、ちょうど電車にご執心だった頃には
まだ走っていたはずですが、おそらく地方路線などで使用されていたため、直に見ることができなかったのだと思います。
181系電車は、旧国鉄が設計・製造した直流用特急形電車。 このボンネットは高速運転に備えて運転士の視界を確保するため 運転台を高くしているそうです。 また電動発電機や空気圧縮機といった騒音発生源を客室からできるだけ遠ざけるため、 運転台前部にボンネットを設けてその中に収納するよう配慮されているそうです。 |
 |
これって気動車なんですね。 ちなみに気動車とは「運転に必要な動力源として熱機関を搭載して自走する鉄道車両」のことです。
現在だと気動車と言えばディーゼル車輌が一般的だと思いますが、このキハ41000はガソリン動車なんだそうです。
しかし、このデザインは味があります。
キハ41000形気動車は、昭和7年から昭和11年に国鉄の前身である鉄道省が開発した機械式ガソリン動車です。 製造は140輌。 最初の36輌はキハ36900を名乗りましたが増備車に合わせ41000に改番されました。 その後も搭載エンジンの載せ変えや改造時に形式変更がおこなわれ最終的にはキハ04・キハ05になりました。 塗色は当初ぶどう色1号でしたが昭和10年頃青/黄褐色に変更し、昭和34頃からはクリーム/朱色となりました。 昭和41年までに国鉄上からは姿を消しましたが、半数近くが地方私鉄に払い下げられたためその後も姿が見られたそうです。 |
 |
昔は、この赤いカラーリングの電気機関車に憧れていたんですよね。 当時、電気機関車は青地にクリーム色のラインの配色が一般的で、
実際にそれしか見たことがありませんでした。 当時聞いた話だと、合っているかは不明ですが、直流電気機関車は青字にクリーム色ラインで、
交流(交直流!?)電気機関車は赤い塗装って言ってたんですよね。 実際この赤い電気機関車が運用されていたのは、東北地方や北海道だったですよね。
ED75形電気機関車は、旧国鉄が1963年から製造した交流用電気機関車です。 1963年に常磐線が平駅(現・いわき駅)まで交流電化 開業するのに伴い、広汎な運用に供するため汎用性を重視して設計された機関車です。 投入開始以来、当初構想の東北・常磐地区のほか、北海道や九州にも投入され、事実上の標準型として1976年までに302輌が製造されました。 |
 |
寝台特急あさかぜの最後部車輌ナハネフ22形式客車です。 この「ナハネフ」の文字のうち「ネ」の字が入っているのは寝台用の車輌を意味します。
「寝床」の「ネ」なんだそうですよ。 この車輌は国鉄初の固定編成寝台特急用客車で、空気バネ台車や防音2重窓を採用しているんだそうです。
管理人も昔「あさかぜ」「富士」「さくら」「みずほ」にはよく乗りましたが、そこ頃はすでに14形寝台車になっていたと思います。 でも、
一回だけ、寝台急行「銀河」でこの車輌を見たことがあるかもしれません。 その頃は「絵入りサインマーク」になっていたと思います。
1964〜1970年にかけて1〜26が日本車輌製造のみで製造された2等寝台緩急車です。 全車寝台化の方針変更により、 ナハフ20形に代わって製造が開始されました。 非貫通式となっており、車掌室と展望室が設けられています。 寝台はナハネ20形と同様の3段式が8ボックス48人分設置されています。 車掌室とは別に乗務員室も設置されている。 JRに継承された車両は1996年に廃車となり、同年に形式消滅しました。 |
 |
この茶色い電気機関車も非常にいい味だしています。 蒸気機関車に続いてお気に入りなのが、ED13,17,51,52やEF10番台の
電気機関車です。 特に前部デッキがついた車輌が形として非常い美しく感じます。
ED17形は、旧国鉄並びにその前身となる鉄道省が、昭和5年から昭和25年にかけて、旅客用電気機関車等の改造により 製作した直流用電気機関車です。 本形式の改造種車となったのは、大正12年から大正14年にかけてイギリスから輸入された 電気機関車群です。 いずれもイングリッシュ・エレクトリック社で製造されたもので、これらの英国電気製電気機関車は、 同社のディック・カー工場で製造されたことから、「ディッカー」あるいは「デッカー」と呼ばれました。 また、その無骨な外観から鉄道ファンによって「クロコダイル」という愛称も与えられています。 |
 |
これは何の車輌の椅子だか分かりますか?? これは新幹線0系のシートです。 子供のころ広島の田舎に行くときに よく乗りました。 そういえばこの座面が青、背もたれが青と薄緑のシート、でヘッドレストに白い布がかけられていました。 今の新幹線の座席は非常にあか抜けた美しい感じのシートですが、今0系のシートを改めて見ると、なにか武骨で座り心地悪そうですね(笑) |
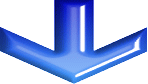
〜 食 事 処 〜
鉄道博物館の中には食事ができる施設が2箇所あります。 1つは1階にあるレストラン「日本食堂」です。 2つ目は2階にあるレストラン「TD」です。
今回両方とも行きましたよ〜。 1階にある「日本食堂」は昔あった食堂車に出てくる料理をいただけます。 特にカツカレーは
懐かしく思い出す方も多いのではないでしょうか。 メニュー名も「懐かしい食堂車のカツカレー」といいます。 他のメニューにも「懐かしい食堂車〜」
シリーズありますよ。 ミートソースとかハヤシライスとかね。 また列車乗務員賄い丼ってのもありました。 HPを見ると今回のは「第9段」って
書いてあったので、もう前に8種類あったんですね。 2階にある「TD」は普通のレストランです。 ハンバーグ定食やパン、ソフトクリーム、
ドリンクバーなどお子様が喜びそうなメニューが豊富です。
|
|
|
|